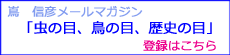歴史認識に踏み込もう
安倍外交は、一見すると華やかに見える。自ら東南アジア、EU、アフリカなどを訪れ、こもりがちだった日本のイメージを内外にアピールしているからだろう。安倍首相だけでなく麻生副総理、岸田外相ら閣僚らも手分けして各国をまわり国際機関の会議に参加している。野党がバラバラな国会情勢も政権首脳の海外出張を容易にさせているのかもしれない。
しかし外交で問われるのは訪問国の数だけではない。日本にとって重要な国と中身の濃い、将来への展望が明るくなる外交談議、交渉をどれだけ積み重ねてこられたかどうかだ。その点からみると、今の日本外交は何か心もとない。
その理由ははっきりしている。日本の隣国であり、歴史的にも長い縁のある中国、韓国はじめ問題を抱えるアメリカ、ロシア、北朝鮮などの近隣国との関係が前進せず、腹を割った話合いをしているようにも見えないからだ。秋に相次ぐ国際会議の場で、習近平・中国国家主席と立ち話ぐらいはできるだろう、といった外務省筋の憶測が流れたりすると、日本側がへり下って見え、もの悲しくさえ感じてしまう。
各国との間には、尖閣、竹島、TPP、北方領土など、それぞれ厄介な課題を抱えてはいる。しかしもっと根深く根本にあるのは、やはり歴史認識問題だろう。日本は過去の村山首相、河野議長などの“謝罪”談話で一応のケリがついたと考えている。だが政権が変わると、それらの談話を踏襲した政治姿勢で臨むかが、いつも話題となる。政権によっては何とも歯切れの悪い形で認めるものの、そこには潔さがみられないと感じられてしまい、また蒸し返されるのだ。
南京の虐殺数とか鉄道爆破事件など個々の事件の原因、被害・加害の数などにそれぞれの見解の違いがあることは、これまでの論争で明らかだ。しかし今問題になっている「歴史認識」とは、日本がアジア諸国に侵略し多数のアジア人を死傷させたこと、他国の領土に満州国などを建設し主権を侵害したこと等々、歴史の大本のところで日本は太平洋戦争の経緯と侵略行為を本当に反省しているのか、という点を問われているのだと思う。
あの戦争を繰り返してきたドイツとフランスも欧州復興の大局に立って50年近く話合い、和解へとこぎつけた。その独仏も最近、ユーロ危機を巡って若い世代が互いに反発を強めだしたと伝えられるが、政治家たちが抑えにかかっていると聞く。「歴史認識問題は後世の歴史家に任せたい」というのではなく、今の政治家が話し合い、国民に説得するのが真のステーツマンの役割ではなかろうか。
この歴史問題は日本と中・韓、北朝鮮の問題だけではない。最近アメリカも日・中・韓の対立を懸念しはじめている。成長センターであるアジアで中心の日・中・韓がいつまでももめていては、TPPやアジア諸国との経済協力、安全保障の問題などにも支障が出るからだ。またロシアも焦眉のシベリア開発には中・韓・北朝鮮だけでなく日本の技術支援などが欲しくて仕方がないのだ。
最近中国は、昨秋までとは違い、尖閣の棚上げ論や先送り論のシグナルを様々な場面で送ってきている。これに対し日本は「尖閣は日本固有の領土であり、話合うべき問題はない」と突っぱねている。しかし今や世界中は尖閣問題で日中がもめていることを知っている。中国が投げてきている曲球を全く受け止めず無視するのか、日本の領土であるという主張を変えることなくうまく話合いにもってゆくのか。ここは政府と外務省が良いワーディング(外交用語)を考える知恵の見せ所だろう。中国は今環境問題やバブルの清算に頭を悩ませている。大局に立った譲り合いが望まれる。【電気新聞 2013年8月26日】