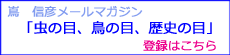戦後レジーム改革論の危うさ ナショナリズム流行で良いのか
「安倍さんは、オバマ大統領と必ずしも相性があっていないみたいだな。むしろロシアのプーチン大統領の方に親近感があるんじゃないだろうか」──安倍首相の側近がふともらした感想だ。
互いに何を言っても後味の悪さを残さず〝良い個人的関係〟を作るのが首脳同士ではもっとも大事なことだ。レーガン大統領と中曽根康弘首相は〝ロン・ヤス関係〟、小泉純一郎首相も気安く言いたいことを言い合っても、気まずい雰囲気を周囲に感じさせなかった。こうした首脳関係が出来ていると、厄介な二国間問題があっても周囲には〝最後は2人が何とかまとめてくれるだろう〟という安心感が漂い、結果的にも成功する例を何度か見てきた。ただその関係を作りあげるには、相手が国内的、対外的に窮地に陥っている時に〝ツーカー〟で理解して汗をかいて動いてみせる積み重ねも大事になる。
中曽根首相は、レーガンが欧州首脳に直接言いにくいことをよく代弁していたし、小泉首相も対イラク戦争で後方支援に自衛隊を派遣し、仏・独などとは違った対応をみせ喜ばれた。代わりに日米経済摩擦などで日本は大分助けてもらった。
安倍首相の最大のウリの一つは、外交だろう。就任1年で30カ国以上を回り、行った首脳会談は軽く100を超えている。経済人を同行し数々のプロジェクト契約も成立させた。何よりも大きかったのは2020年の東京オリンピック誘致を成功させたことだろう。1年間でこれほど世界を回った首相はこれまでに例をみない。
しかし安倍外交が世界で評価され、うまくやっているという声は決して多くはない。新興国は安倍首相の経済外交に好意をもってくれているが、アメリカ、韓国、中国、最近はEU各国でも批判的論調がふえている。その原因はひとえに靖国参拝であり、その背後にある戦後秩序の見直し、歴史認識、国家主義的思想などに違和感をもっているためではないか。
欧米は大戦後に戦争の総括と反省を二国間や多国間で行い、歴史認識の共通化、人権、多様性の尊重などを育んできた。日本は、表向きでは〝価値観の共有〟を語っているが、本音では平和憲法の成り立ち、歴史認識と歴史教育、中国や朝鮮半島などで不満をもつ政治家や勢力が少なくない。それが安倍政権の登場で「戦後レジーム(体制)の再検討」などの言葉で一括して語られるようになった。しかも、それと相まって特定秘密保護法、国家安全保障局の設置、武器輸出三原則の見直し、教育制度の改革、集団的自衛権の解釈変更、憲法改正などが声高に語られるため、アメリカ、中国、韓国、EUなどとの間でギクシャクした関係が目立ってきたのである。
戦後レジームは敗戦国日本が強くモノを言えない時に押しつけられたものだと考えてしまうと、大国になったいまはもっと主張すべきだとする考えは若者などに受け入れられやすく、安倍政権支持率の高いことにも影響していそうだ。
しかし、日本が敗戦からここまで成長し豊かになったのは、その戦後レジームがあり、その流れを受け入れてきたからだということも忘れてはなるまい。
【財界 2014年5月27日号 第375回】