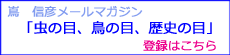物価目標2%は もう不必要!?
日本の消費者物価(CPI)を2%まで上昇させる──この目標は、いまもはたして正しいのだろうか。黒田東彦氏が日銀総裁に就任(2013年3月)すると、低金利・ゼロ金利、金融の巨額な量的緩和政策を実施した。この結果、一時、1㌦70円台まで円高に推移していた円・㌦相場は120円台まで円安に戻り、日本企業は円高不況を脱する。また市場におカネがジャブジャブと注ぎ込まれたことで証券市場にも大量の資金が流れ込み、7000円台まで低落した東証の株価は一時は2万2000円前後まで上昇した。
しかし黒田総裁が目指したCPIは、14年12月末に前年比プラス1.3%に達したものの、ほとんどは1%以下、それも0.5%以下が多く物価上昇の効果は出ていない。一時的な物価高も円安による輸入物価の高騰や消費税が14年4月から8%にあがったことや消費税上げに便乗した値上げなどが背景だった。実際のコアCPIは4月で依然0.3%と低迷中だ。黒田氏は最近「2%に達するのは16年度前半」と到達時を先延ばしした。
これはいくらゼロ金利を維持し、大量の金融緩和を続けても企業や消費者の投資、消費意欲を高めていないということなのではないか。円安になれば企業利益があがり、国内投資がふえて景気が上昇、消費もふえて景気と物価の好循環につながるとみていたが、予測ははずれた。多くの大企業、中堅企業はすでに海外に工場をもち、余剰資金は企業買収と内部留保などにあてて国内投資には向けなかった。また消費者にとっても、全体からするとこの20年間ほとんど所得はふえていなかったし、かつてのように消費への意欲も高まることはなかった。むしろ生活はつつましくなっている。
経済政策の最終的な目的は、国民の生活が安定し安心して暮らせることだろう。だとするなら賃金があがらない中で物価が安定し、CPIが落ち着いていることは決して悪いことではない。政府・日銀はCPIを2%にもっていけば景気の好循環と賃上げが実現すると考えていたが、その見通しはどうやら間違っていたのではないか。日本企業や消費者のここ何年かの行動、ビジネス・ライフスタイルをみるとあきらかにこれまでの経済予測のように動いてはいない。
最近の主要100社の調査(朝日新聞)によると円相場は「115円~120円未満」が適正という企業が多く、「120円以上の円安になると原材料コストがあがるし社員の生活面からみても物価が上昇し単純に良いとはいえない」とする輸出企業がふえている。
金融と財政は経済政策の手段であり、経済を好循環に導くには政府のいう〝第三の矢〟、すなわちイノベーションなどによって新たなビジネス、雇用などを生み出す環境を整えることが本筋だろう。日銀が国債を買い続けて超金融緩和を続けることは副作用を大きくすることにもつながりかねない。アメリカが金利をあげたらまた大混乱しよう。もう物価上昇目標は取り下げてもよいのではないか。黒田・日銀は十分に役割をはたした。
【財界 2015年8月4日号】