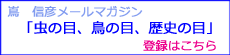日本は1000年ぶりの地質大変動時代に! ―2030年代に再び巨大地震か―

先日、火山地質学や地球変動学の権威である京都大学大学院教授・鎌田浩毅氏にお会いして最近の地震や火山爆発などの話を伺った。
まず、鎌田教授の服装にびっくりさせられた。カーキ色のジャンパーのような上着に火山を思わすような真っ赤な図柄が描かれ、上着の下はこれまたユニークな模様のTシャツ姿だ。夏には火山模様の浴衣を着て講義をすることもあるという。毎週の講義に変えるので火山、地質などをデザインした服は50着以上に及び「ボーナスは服で消えました」と笑う。またその話ぶりも猛烈で、まるで火山が火を噴いているようにエネルギッシュだ。京大で1、2位を争う名物授業で聴講生は400人以上の人気という。
―活断層は日本に2000カ所―
鎌田教授によれば、5年前の3.11東日本大震災以降、日本は1000年ぶりの大変動の時代に入り、今後想定外の地震や噴火の自然災害が次々と続くそうだ。東日本大震災だけをとってもその余震などは30年続くという。東日本大震災の震源域は南北500キロメートル、東西200キロメートルに及ぶ広さだった。
日本には岩盤の弱い活断層といわれる場所が2,000カ所あり、うち100カ所が活動中とされる。原発の下の活断層が話題になるが、日本は活断層の上にあるようなものなのだ。地球科学からみると、東日本大震災をおこした地下の活動は全く終わっておらず、静穏期になるまでに数十年はかかるそうだ。
一番心配されているのは南海トラフ巨大地震だ。日本列島はプレートと呼ばれる4つの岩盤が押し合いへし合いしている変動地域の上にあり、特に東海、東南海、南海の3つが連動しておこる南海トラフ巨大地震が同時に来ると巨大災害になるという。静岡沖から宮崎沖までの深海4,000メートル地帯では、ほぼ間違いなく2030~2040年(2035年プラスマイナス5年)のうちに大地震がおこるという指摘。その場合、マグニチュードは9.1以上、20~35メートルの津波、32万3,000人の死傷者、被害額200兆円以上と予測されている。日本は4つのプレートがひしめいているので、“4つの恐怖”があるといわれる。海の地震、陸の地震、西日本震災、火山噴火である。近年の雲仙普賢岳、東京の三原山、鹿児島の桜島、御嶽山、西之島の噴火等では大きな話題となった。マグニチュード9クラスの巨大地震が発生すると、同じ海域内で10年以上たってから大地震がおきることがある。たとえば、明治三陸沖地震(1896年)で死者2万1,000人以上を出したが、それから37年後に昭和三陸沖地震(マグニチュード8.1)が発生、3,000人の犠牲者を出した。
私たち人間の時間軸は普通1週間程度だし、企業の経営計画も1年、中長期でも3~5年程度だが、地球科学では50年、100年などが当たり前なのだ。普通30~50年に1回と聞けば、自分の生きているうちには来ないと考える。しかし、最近の災害は40~50年ぶりとか、70歳台の老人が「こんな災害、生まれてから初めて」などと話すのをよく聞く。近年は世界的にも40~50年ぶりの災害が発生する時代になっているのかもしれない。
―9世紀の日本と酷似する現代、富士山の爆発も―
鎌田教授によれば現代は9世紀の日本と酷似しているという。869年に発生した貞観地震は今回の東日本大震災と同じく東北地方で起き、9年後には相模・武蔵地震という直下型地震(マグニチュード7.4)が関東南部で発生、さらにその9年後の887年(仁和3年)には、仁和地震と呼ばれる巨大地震(マグニチュード9クラス)がおきて大津波が発生、その間に富士山、阿蘇山、開聞岳などが噴火した。21世紀にあてはめると、東日本大震災がおきた2011年の9年後の2020年に東京オリンピックが開かれるが、単純計算ではその頃に首都圏に近い関東で直下型地震がおき、9年後の29年過ぎに南海トラフ巨大地震がおこる懸念があるということになる。
気になるのは富士山の噴火だろう。富士山にはマグマ溜まりが地下20キロメートルあたりにあり、火山学的には100%噴火するスタンバイ状態だという。一番ひどいケースは山体が崩壊することもあり得るといい、火砕流の発生、山体変容など5つのケースが予測されているそうだ。ただ地震は突然来るが、火山の噴火には1週間から1カ月ぐらいの余裕があるそうで予知は可能のようだ。
―「想定外」の事態に備えよ―
大変動時代に入ると突発的に地震や噴火がおきるので「予測と制御」が機能しにくい。従って常に「想定外」の事態を考えておき、突発的出来事に対して柔軟に対応する「しなやかさ」を普段から持ち、考えておくことが必要だという。企業も東京一極集中にこだわらず、東京で大災害がおきた場合の第二、第三の対応を考えておくことが重要なのだろう。
鎌田教授は、学生時代に地質学を専攻したが、授業にも本にも興味が持てず、さっさと卒業して普通の企業に就職したいと考えていた。ところが“受けては落ち”の連続で、結局通産省の研究所に入って研究を続けている時、阿蘇山の9万年前の噴火跡のカルデラ(直径約20キロメートルの陥没)を見て、その広大さと、エネルギーのすごさを実感して本気で勉強に取り組むようになったという。いま阿蘇山のカルデラを形成するような爆発があると、九州全体に20センチメートル、大阪で10センチメートル、東京でも5センチメートルは積もる火山灰が降り注ぐだろうと想定されているそうだ。自分の人生を振り返ると、本物の自然と良い師匠に出会ったことで火山、地質学の道に入ることになったといい、その経験から対象の学問、勉強だけでなく周辺の広い知識も持てるような“一生ものの勉強”が大事で、そこから人生に必要な“直感”も磨かれていくと説く。
(8月21日と28日の日曜午後9時半からTBSラジオで2回にわたりインタビューの模様を放送予定。詳細は嶌信彦オフィシャルサイト等で発表)
【TSR情報 2016年7月27日】