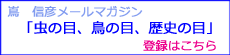大学入試センター試験
1月下旬に恒例の大学入試センター試験が行なわれた。毎年この時期は普段より寒く雪の降るところも少なくない。だからセンター試験の日は、天気と受験生の記事や電車、列車の遅れ、試験問題とか試験管理のミスなどの報道が定番となっている。私はいつも〝われわれの時代(1960年代)にはセンター試験なんてなかったな。このセンター試験と各大学が独自に実施する試験との関係はどうなっているのだろう〟などと思いながら、その実態はよくわからないまますごしてきた。
ことしは、日曜日がヒマだったので、センター試験の内容をチラッと見てみた。例年だと、試験問題の出ている新聞ページは飛ばして読まないのが習慣だった。ただ、この1、2年はいくつかの私立大学から、私が以前に書いた本の一部を試験問題に使ったといった連絡と事後承諾の許可要請が来たりするため、今回はセンターでは一体どんな問題が出て、どの程度のレベルなのか、と興味をもったのだ。
もともと私は理系は弱いので見向きもしなかったが、国語や社会、歴史、政治・経済なら多少はできると考え問題のページを開いてみた。国語では小林秀雄の長文や牧野信一の小説「地球儀」の短編全文、「松陰中納言物語」の一節(古文)、張耒「張耒集」からとった漢文の一節など実に多彩で高級である。歴史問題も日本古代の宗教・政治や中世の文化・宗教のほか、沖縄と北海道の視点から近代史や戦後史のテーマが提起されており、日本の北端と南端から歴史を読み解く問題設定にちょっと驚いた。歴史教育は近・現代がおろそかと言われるが、現代の北方領土や沖縄問題をとりあげた問題作成者の心意気のようなものを感じたからである。
だが解答方式が気に食わなかった。国語、歴史、地理などすべて四つ、五つの選択肢の中から正解を選び記号を記入するやり方なのだ。採点にはその方が簡単だし、文章式の解答だと採点者の主観が入り込むので、試験方法としてはこのやり方が正しいのだろう。しかし、これでは学生に〝考えさせて自分の推論や立論などを書く〟という思考テストにはならないと思うからだ。
問題はすべて難しく、私には選択肢のヒントがあっても合格点はとれそうになかった。ただ、提起された文章から自分なりの立論を行ない小論を書けという試験ならば、今の学生にそうむざむざと敗北すまいという思いは残った。理系科目は、基礎的な理論、数理、科学的知識から解くことを求められるので〝考える力〟を要するだろう。
私は白鴎大学の教壇で約10年にわたり国際関係論の講座を担当、毎回講義後に5分間与えて葉書大よりやや大き目の用紙に前週などにおきた国際問題等の小論を書かせた。すると2カ月目ぐらいから自分の主張、意見を書く学生がふえた。面白いペーパーは翌週に学生達の前で読み上げると一層効果的だった。考える試験問題、考える学生たちを育てたい。【財界 2013年2月26日号 第345回 】