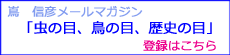出てゆくばかりが能ではない 対日投資の魅力を世界に売ろう
タイ・バンコク近郊のマハチャイは、水産業の中心地として知られる。タイ湾近辺の河口にある漁港には魚介類が水揚げされ、工場で加工されて国の内外に送られるのだ。日系の工場も少なくない。
マハチャイの漁船員は約3万人にのぼるとされるが、9割近くはミャンマー人など外国人だという。90年代に入ってから外国人がふえ、きつい仕事を近くの賃金の安いミャンマー、ラオス、カンボジアなどからまかない、タイ人は都会に出て行ってしまうらしい。かつての日本でみられた農村と都市の関係がアジアの新興国でもものすごいスピードで進んでいるのだ。
中間層がふえると、学歴も高い人がふえ、ホワイトカラーやIT関係などの仕事につきたがる。するといわゆる3K(きつい、汚い、危険)といった仕事を敬遠し、賃金の安い農村部からの出稼ぎや外国人労働に頼る割合がふえていく。新興国が成長する過程でどこもが通る道筋で、歴史をみれば洋の東西を問わない現象だ。
さらに新興国が先進国入りしてくると賃金の安いところへ海外投資を拡大し、国内産業が空洞化してゆく。かつてのイギリスはその典型で、日本もその道を歩み始めている。とくにグローバル化経済、IT化、ロボット化などが進むと雇用や税収、人口減少などと関係してくる。
1970〜80年代に英国病、ウィンブルドン現象と呼ばれ、衰退していったかつての大英帝国は、サッチャー首相の登場で金融立国として一時は蘇えるかに見えたが、リーマンショック、ユーロ危機で再びもがき始めている。その点、ドイツはマイスター制度が健全に残り、EUの技術・輸出立国としていまやヨーロッパの盟主的立場になった。フランスは農業、原子力、観光、小売りなど、イタリアも中小企業の歴史やブランド、観光などでしぶとく、したたかに存在感を発揮している。
さて日本である。途上国から近代国家になり、列強の仲間入りをしたものの、無謀な戦争ですべては灰塵に帰してしまったが、戦後わずか20年余で世界GDP第2位となりその地位を維持し続けた。しかし中国が2010年にその座を奪い、アメリカと〝新しい大国の関係〟を作ろうとしている。さらにインドやインドネシアなどの人口大国の追い上げも激しい。【財界 2013年9月10日号 第358回】
そんな中で、老舗のイギリスが再び製造業の強化に動き出したという記事があった。今やイギリスのGDPに占める製造業の割合は10%。しかし金融・サービスに依存しすぎた反省が出ているというのだ。むしろ製造業は雇用や新しい経済価値を生む公共財と考えるべきで、賃金の安い国へ工場を移す企業戦略は〝怠け者の考え〟だという思想がEU主要国に高まっているらしい。
高い技術で生産性を高め、イノベーションによって新たな魅力的な産業を生み出すことこそ先進工業国家の生きる道。先進国は高い人的能力、開発力、マーケティング、技術力などすべてを兼ね備えているではないか、というのだ。日本も対外投資ばかりでなく対日投資の基礎的魅力をもっと訴えたらどうか。【財界 2013年9月10日号 第358回】