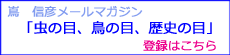黄信号灯った安倍政権?
”安倍一極”といわれてきた政局に変動の兆しが見え隠れしてきた。そもそもは、11本の安保法制をひとまとめにして通そうとした手軽な発想がいけなかったのだろう。ふつうなら1本ずつ通すにも2、3ヵ月かかるといわれた国の基本、しかも憲法9条を拡大解釈し、法律で日本の安保法制を急いで可決しようとしたところに無理があった。
憲法9条はアメリカによる”押しつけ”だという議論が多い。たしかに制定過程をみるとアメリカが日本に二度と戦争をおこさせない、武力をもたせない--などの基本原則を求め、受け入れたのは事実に近かろう。あの悲惨な太平洋戦争を二度とおこさせないために憲法上のタガをはめたのだ。当時の日本国民も敗戦のおろかさを身に沁みていたから、大多数の人は戦後日本が生きる大道としてこれを受け入れたのである。
しかしその後、警察予備隊という名で自衛隊への道をつくり、朝鮮戦争や中華人民共和国の成立などアジア情勢の変化に伴い日本の防衛は日米同盟と自衛隊の強化という形で進行してきた。だが、それでも”日本は先行をしない””他国に攻め入らず専守防衛だけにつとめる”という基本原則は憲法9条の旗のもとに日本人の多くのコンセンサスとして今日まで生きてきた。。またこの憲法9条の歯止めが国際社会にも広く認知され、防衛費の上限(GDPの3%以下)と片務的な日米安保条約を守ってきたからこそ、戦後70年の平和な経済大国を築き得たと多くの国民は思ってきたのではないか。
それが突然”憲法は変えないが国際情勢は緊迫度をましてきた”ので、憲法はそのままにしておいて安保法制だけを変えるといわれても、国民はとまどうだけだろう。本当に突然、中国との戦争が始まるのか、北朝鮮がミサイルを日本に向け発射するのか、ホルムズ海峡が封鎖されるのか--どれも抽象論としてはわかっても今日、明日のことなのかという疑問がついてまわる。それよりアメリカがアジア太平洋などから軍事力を減らすから、その穴埋めをして欲しいという春の日米首脳会談の約束があったから急いでいるのだろうという推測の方がリアリティをもってしまうのだ。
憲法学者の多数が、この安保法制は立憲主義に反すると主張し、リタイアした老人や主婦、ノンポリ的な学生が不気味さを感じて反対デモなどに参加、地方議会も次々と反対声明を出す――これらの現象を政治家たちはどうみているのだろうか。
そこへもってきて、新国立競技場の巨額な建設費と誰が責任者かわからない決め方に多くの人はあきれかえっている。何か本質的な議論を真面目に討論せず、細かな枝葉の議論に終始していた感じが強かっただけに、余計問題の本質が見えず、そのことが一層国民をいらだたせたようにみえる。さすがに安倍政権もコトの深刻さに気づいてきたようだ。
競技場計画を白紙に戻したが、内閣支持率は30%台に落ちたままだ。自民党内では一極支配の安倍政権だが、支持率が30%を切ってくると明らかに黄信号となる。国民は忘れやすいが、今回ははたして簡単に忘れるだろうか。8月15日の天皇のお言葉の発し方によっては一層窮地に立たされるかもしれない。【財界 2015年9月8日号】