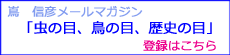魂を吹き込む
先日、文楽の世界で人間国宝の初代・故吉田玉男さんの後を継いだ二代目・吉田玉男さん(襲名前は吉田玉女(たまめ))をインタビューする機会を得た。文楽は気になる存在だったが、実際に見たのは10年以上前に一、二度あるだけだった。歌舞伎と似た演目を人形で演じ、表現する独特の伝統芸能で大阪から発生し、江戸時代前期から続いてきて、最近再び人気が出ている。
インタビュー前に初代の映像を見た。人形が主役だが、もう一方の主役は”語り(義太夫)”で、やはり人間国宝だった七代目竹本住大夫氏が熱のこもった語調で芝居の筋を唄いあげる。観客はその語りと人形の動きにいつしか釘付けになり文楽の世界に誘い込まれるのだ。
人形は顔と右手、左手、両足を扱う3人の遣い手で操っている。一体の人形を3人で動かしているのだ。主遣いは主役で素顔で人形を遣い、足と手は黒頭巾と黒装束の人が動かす。一人前になるには足で10年、左で15年、主遣いになるには20年の修業が必要といい、人形の顔の表情、手足を操りながら語りとも合わせるわけだから大変な修行と年月を要する伝統芸能なのだ。しかも主役はあくまで人形であり、人は黒衣に徹するというから実に地味な役割を担っている。一体の人形を動かすには3人が必要で舞台に10体も登場する絵本太功記「大徳寺焼香の段」などでは30人が左右に動くという。
しかし、語りを聞きながら舞台を見ているといつの間にか黒衣や主遣いの人達は目に入らなくなり、人形の動きや表情だけに惹きつけられるから不思議だ。歌舞伎は人間だけが演ずるが、文楽の方が真実味や迫力を感じてしまうところに数百年も続いてきた伝統芸能の魅力があるのだろう。
人形は遣われていない時は、単なる物体にすぎない。そこに息を吹き込み、キラキラと瞬く目や手足の動きをつけ、まるで人間以上に躍動してみせるところに人形遣いの真骨頂があるのだろう。
吉田さんによれば、一体一体の人形の衣装は、自らの手で毎回色やデザインを考え、実際に自分で縫うのだという。上演毎にそんなに手間をかけているのかと心底驚いた。しかしよく考えてみると、そこまでして人形に愛情を込め手作りしているからこそ、自由自在に操り、人形と一体になれるのかなと感ずる。まさに舞台に立つまでにも人形に息を吹き込み、魂を入れているのだ。
日本のみならず、世界中が合理化、IT化、ロボット化、省力化などに邁進し、コストをかけないことを良しとする風潮が大はやりだ。しかし、最近の鉄道事故や工場爆発、電力事故、欠陥自動車などの事件をみていると、科学信仰や合理化の行き過ぎに警告が発せられている気がしてくる。
お百姓さんが丹精こめて作ったおコメなのだから一粒たりとも残すなとか、名大工さんはいつも仕事を終えた後の道具の手入れを怠らない、野球の名選手は練習後のグローブやバット、球の後始末、手入れを大事にしているなどといわれる。
日本では、自然にも魂が宿るとされ、工業化、科学時代になっても製品や機械なども単なるモノではなく魂が宿っていると考える人が少なくなかった。
文楽の人形は糸などでつながれて作られたもので、床においておくとまさにモノそのものだ。しかし、ひとたび人形の遣い手が、語りに合わせて動かし始めると、一挙に息吹きと魂が吹き込まれ、時には人間の役者が演ずる以上に観客の心をつかむ。人形劇とはいえ、数百年も日本人に親しまれ、人間国宝まで生み出す伝統芸能、文化にまで成長してきたのだ。モノやカネ、IT文化全盛時代だからこそ魂を入れる意味が問われているのではないか。
【電気新聞 2015年9月14日】