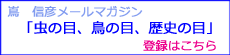コロナでみせた地方の底力

新型コロナウイルス感染症が長期化する傾向をみせるにつけ、地方自治体が独自に対策を打ち出し始めている。地方によっては感染症拡大が急速化したため、全国一律の方針を打ち出そうとする国の対策を待っていられないからだ。地方が地域の事情に応じて独自に動くことは、地方分権の流れを早め地方の特色を生かす大きなきっかけになるかもしれない。
北海道は、今年2月25日に感染者数で東京都を抜いて全国最多になったため、翌26日に北海道の全公立小・中学校約1600校を対象に1週間程度の休校要請を出した。安倍元首相が全国の小・中・高校への休校要請を表明したのは一日遅れの27日だった。北海道は、さらに28日に「緊急事態宣言」と「外出自粛要請」も打ち出した。
北海道の鈴木直道知事によると、「国に先立って宣言を出すことに不安やためらいはあったが、全道で広範に感染が広がっている状況があり、学校関係者の感染が相次いで子供や保護者、現場に不安が生じていた。しかし、25日の段階では国も方向性が定まっていない状況だった。ただ北海道では時間がなく、目の前に困っている人がいる中でどういう対策を打つのか、知事の責任で決断しなければならない緊迫した情勢の中で決断せざるを得なかった。また緊急事態宣言などを出す前には政府の専門家会議のメンバーから助言をもらっていた。さらに29日に安倍首相にお会いして北海道のような感染状況がいずれ東京やその他の地域に拡大するかもしれないと訴えた。あの頃は緊急事態宣言などの問題について全国的な対策を取っていこうというところまで国はまだなっていなかった」と指摘する。
2月半ばに病院の院内感染が国内で初めて明らかになった和歌山県の仁坂吉伸知事は、「そもそも感染症への対応は都道府県知事の権限であり義務。和歌山では早期発見、早期隔離、徹底した行動履歴調査という基本に忠実に従った。国は37.5度以上の発熱が4日続くまでは受診を控えて、と言っていましたが、和歌山はその方針に従わないとはっきり言った。風邪気味の人はどんどんクリニックへ行ってX線やCTを撮ってもらう。肺炎の疑いのある人だけが保健所に行ってPCR検査を受ける。その方が合理的だから、国が何と言おうと従わなかった。頼るべきところは国に頼るけれど、地方で判断すべきところは地方がやるというのが基本だと思う」と言い、「日本は保健所の立て直しをしっかり見直すべきで、保健医療行政をもっと機能させるべきだ」という。米ワシントン・ポスト紙は3月23日にこの迅速な対策を「和歌山モデル」として称賛した。(※1)
さらに休業要請の範囲を巡って小池都知事と西村康稔・経済再生相の間では意見の相違を巡って対立した。国は社会の混乱を避けたいと対象範囲を絞ろうとしたのに対し、小池知事は「命ファースト」を掲げて対象を広げるよう主張し、結局、東京都の言い分がほぼ通ったとされる。
また大阪府の吉村洋文知事は5月5日に「大阪モデル」を発表し、休業要請の解除基準や、大阪・兵庫間の往来自粛、大学と協力してワクチン開発を進める――などの方針を打ち出し存在感を示した。
地方は、現場の声を直接聞き肌感覚がある上、住民の命に関わることだけに迅速に対応し、発信がいつになく多かったのだろう。一方の政府は専門家会議の声などに依存しすぎ、地方の生の声、実態把握に弱かったといえよう。今後コロナ危機の第三波がどのような形でやってくるのか、地方は実情をつかんでどんどん政府に情報と対策を提案していき、政府もこうした経験を元に地方分権の実をあげてゆくことを考えてもいいのではないか。
【TSR情報 2020年10月1日】
(※1)「A region in Japan launched its own coronavirus fight. It’s now called a ‘model’ in local action.」3月23日 ワシントンポスト
画像:和歌山県公式サイトより