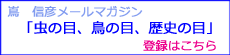増刷決定&11日の公明新聞に新著ノンフィクション「日本兵捕虜はシルクロードにオペラハウスを建てた」の書評が掲載
スタッフです。11日の公明新聞に嶌の新著ノンフィクション「日本兵捕虜はシルクロードにオペラハウスを建てた」(角川書店)の書評が掲載されました。
評者は法政大学名誉教授 川成洋様。
なお、本日増刷が決定しましたので、長期でお待ちいただいている方ももう少し早くお手元に届くものと思われます。今週土曜日に行なわれる日本ウズベキスタン協会の新年会ではサイン本を発売しますので、早く読まれたい方はそちらにお越しいただけると幸いです。
今回新年会は、戦後70周年記念にふさわしいゲストがお越しになります。本邦初公開の映像など、詳細は書評後のリンクを参照ください。
記事抜粋
昨年10月10日、第二次世界大戦直後にソ連に抑留された日本人の570点の記録が、ユネスコの「世界記録遺産」に登録された。
太平洋戦争の末期、1945年8月9日零時、突如、日ソ中立条約を破棄し、174万人ものソ連軍が満州・北朝鮮、ついで南樺太・千島列島・北方四島に侵攻した。さらに日本軍将兵と民間人をソ連に強制連行したのだった。その数は約60万人。彼らは、飢餓・重労働・酷寒の「シベリア三重苦」のために約10万人の犠牲者を出した。
本書によると、若干24歳の永田行夫大尉指揮の457人の日本兵捕虜の抑留地は、幸運にも、シベリアよりはるか南方の、ウズベク共和国首都タシケントであった。緯度的に青森県に相当するこの町は、大航海時代が開幕する15世紀末まで、シルクロードの重要な街道町であった。
永田隊は、軍隊経験の浅い若き野戦航空修理廠の技術兵部隊であり、従って、彼らの任務は、戦争のために建設中断したオペラハウス「ナボイ劇場」の完成、それも革命30周年を記念する47年11月までに、であった。彼らは「無事全員が帰国する」ことを自らの至上命令と課し、この大事業に着手する。彼らの器用さ、想像力の豊かさ、そして勤勉さなどに近隣の住民たちが瞠目するだけではなく、政府高官も視察に来る。他の収容所で跋扈していた「民主運動」や権力闘争などは、この世間知らずの将校と職人魂の集団とは全く無縁であった。作業中に2人の仲間が事故死するが、2年後、ビザンチン風3階建て(地下1階)、1400席の壮麗かつ堅牢な劇場を完成する。それがロシア4大劇場の1つとして称賛され、また66年4月の直下型大地震においても悠然と屹立していたのである。
永田隊は、異郷において縲絏の辱しめをうけながらも、日本人としての矜持と意地を最後の瞬間まで維持してこの大事業に挑戦したのだ。これが、今日でも現地の人々の心を動かし、「日本人伝説」となって語り継がれている。
以上

画像は本書にも登場する若松律衛氏が平成10年(1998年)4月にナボイ劇場を訪問された際に撮られたものを嶌に寄せられたもの。帰国から50年後のナボイ劇場との画像。
※23日に開催される日本ウズベキスタン協会の新年会、ウズベキスタンからゲストをお迎えし抑留に関する映像やお話を伺うトークの会に関する詳細はこちら を参照ください。